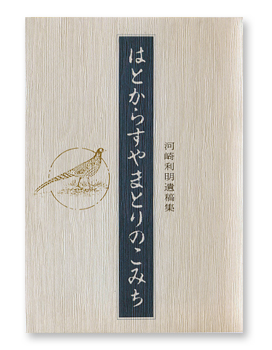父・河崎利明 遺稿集
祖父と祖母
父・河崎利明 遺稿集「はとからすやまとりのこみ」より
祖父は私が六歳の時死に、晩年は私を猫の様に可愛がってくれたので私が直接祖父にもった印象と後年、祖父について聞いた話とでは大そう違う。
一人膳で酒のついた夕食が祖父に出て(他の者はちゃぶ台)、終わると私は祖父のところに行く。右手に箸をもった加藤清正、左手の虎とがチャンチャン戦う話、落語では全く笑ったことのない男が笑い茸の汁を飲まされ「ちっともおかしくない」を繰返しながら次第に笑ってしまう小話などなど、毎晩種を違えて私をたのしませてくれた。
我家はどういう訳か一代替りで働く人間が出る。祖父の父(学者でもあった)も私の父、利市(婿)もそうで、「私は遊ぶ順番だ」と勝手に決めて下谷や葭町、古河の花柳界に出入りし、古河には妾も居て、一軒芸者家を持たせていた。夜はそちらに泊まる方が多かった。
東京でも遊び人で十五世羽左衛門の可江会に入り、芸人とのつきあいも多かった。
ある晩、寄席で三遊亭円朝の来るのが遅れた時、「円朝師匠の来る間に、つなぎに一席」と高座に上がって大拍手をうけ、遅れて来た円朝から煙草入れを貰ったこともあった。
祖母は私が十歳の時に死んだが、格別の印象はない。いつも暗い部屋に静かに坐って縫物などしていた。何時もきちんと座り、八十歳をすぎてからはじめて足をなげ出し膝を手でこするのを見たと母がいっていた。祖母が四十歳代の時、家で宴会があって、祖父は祖母に常磐津の弾き語りを強いた。娘時代その名手だったことを知っていたからである。祖母は黙って嫁入り道具の三味線を出し林中ばりの「乗合船」を弾き語って一座を感心させた。祖母が嫁に来て常磐津を語ったのは、その一回だけだった。
古河出身の小説家、友人の永井路子さんから古河には前にも若杉鳥子という小説家が居たそうで、調べてくれとの依頼をうけた。
すばらしい美人で、祖父の芸者家の養女だった。古河に宮様が見えられた時、接待に出て目にとまり、「どんな家の娘さん?」と聞かれ、「卑しい生まれの者でございます」といった話が残って居る。家業を嫌って東京に出、某新聞社に入り、小説を書き、徳田秋声や長塚節などの目にもとまった。大恋愛のすえ、板倉子爵の弟と結婚、式には我家の人達もよばれた。「歸郷」などという著書も残っているが、読んでみると稚拙なものだ。
鳥子のことを調べていると、廻りはみな妙な態度だった。彼女は祖父が芸者に生ませた子で、皆が知っていて、私だけが知らないことだったからだろう。
鳥子の一人娘黎ちゃんもきれいな少女で、一度鳥子が我家に連れて来た時、私が小学校六年生、少女が三年生位だったろうか。椅子にかけて、足をぶらんぶらんさせているのを見て、これが東京の少女なのだなあと思った。話し掛けたかったが、何故か出来なかった。
六歳の時、塩原の避暑地先から「おぢいさんがもういけません」と呼び戻された。祖父はたらいに氷柱を立てた部屋に寝ていて、「太閤様でも出来なかったぜいたくだ」と父に手を合わせ感謝し、そして死んだ。
祖父は自分で勝手に戒名をつけ、「天弘院江古道楽居士」としていた。天保、弘化のまたがる年に江戸で生れ、古河で死に一生道楽をしたという意味である。父は養子だから道楽という文字は使えない。幸い祖父の愛した徳利に、「楽しみはこの中にあり雪月花」というのがある。それにちなみ祖父の戒名を「天弘院江古三楽居士」としたが、すぐ坊主がそれに宝誉などというつまらぬ言葉に入れ替えて改悪してしまった。
Index
父・河崎利明 遺稿集「はとからすやまとりのこみ」
※ご覧になりたい記事のタイトルをクリックしてください
河崎利明エッセイ、こちらに掲載している以外にも多数あります。
ご希望の方には、お送りしますので、詳しくは「コンタクトフォーム」からお問合せください。